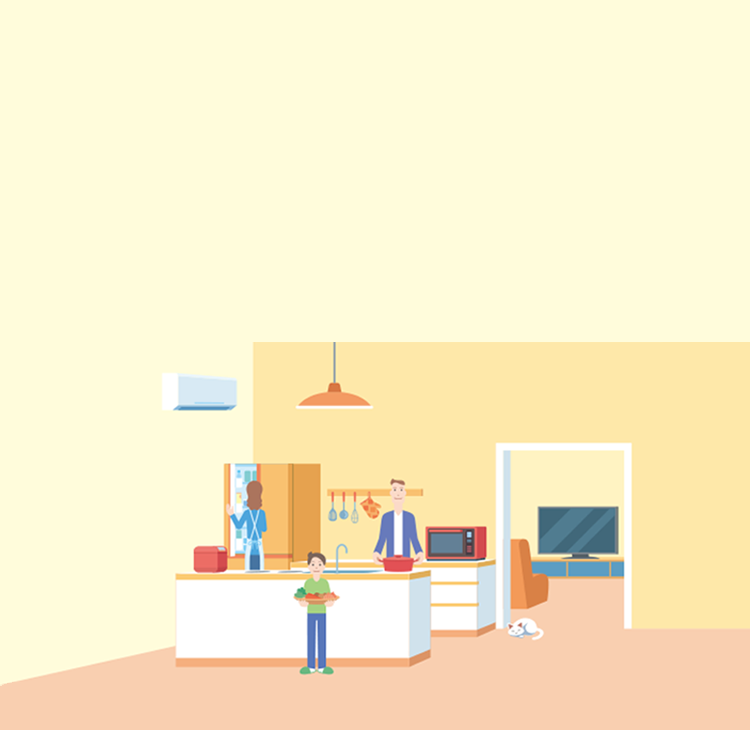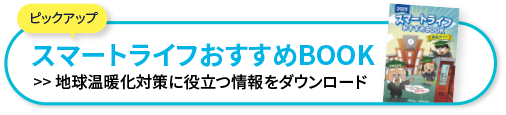詰め込みすぎはNG!冷蔵庫のスッキリ収納で、
詰め込みすぎはNG!冷蔵庫のスッキリ収納で、
電気代も食材もムダをなくします。
コツをつかめば後はラクラク!のスマート収納で、省エネ生活をはじめてみましょう。
冷蔵庫の収納見直しで、省エネに
毎日フル稼働の冷蔵庫。
どこに何があるか、すぐに見つけられますか?忘れられた賞味期限切れ食材が奥の方で場所を占めていませんか?
食材の詰め込みすぎは庫内の冷気が行き届きにくくなるだけでなく、食材を探す間ずっと開けている扉から冷気が逃げるため、庫内温度調節が働き電気を余分に消費します。
家事動線と同じように冷蔵庫を利用する動線を整理して「収納ルール」を作ることで、電気代の節約だけでなく、食材のムダをなくし、探す時間も手間も減らすことができます。
コツをつかめば後はラクラク!のスマート収納で、さっそく省エネ生活をはじめてみましょう。
冷蔵室
食材を“空いたところにとりあえず詰め込む”はゴチャゴチャの元。まずは収納のルール作りが大事です。

-
上段
未開封のもの/賞味期限の長いものをしまいましょう。
取り出しやすいように100円ショップなどの手前のあいたカゴやトレイを利用するのも手。しまう時に賞味期限を大きく書いておくと後からチェックしやすいですね。開封したら、中段へ移動させましょう。 -
ドアポケット
よく使う頻度の高いものは手前に、頻度の低いものは奥にしまいます。
-
チルドルーム
中央にカゴなどを一つ置くことで収納と仕切りの役目を果たします。左は魚、右は肉など場所を決めておくと、取り出しもよりスピーディに。仕切り位置は収納する食材によって自由に移動できます。
-
中段
もっとも目線に入る位置には、開封済みのもの/足の早いもの/よく使うものを、手前のあいたカゴやトレーなどにまとめて収納。
用途別にカゴにセット
たとえば「朝食」用のカゴにはバター、ジャムなど朝食で使うものを一つにまとめて。使うときにはさっと取り出しそのまま食卓へ。戻すのも簡単。
コの字ラック・密閉容器・カゴでより細かな仕切りを
冷蔵庫の備え付けの棚をはずし、コの字ラックと密閉容器・カゴで有効活用。ボトルなど高さのあるものは立てて並べ、頻度が高ければ扉を開けてすぐ手の届く側に配置。薄いものは密閉容器などにまとめます。見渡しやすいだけでなく取り出しやすくなります。

野菜室
気がつくとすぐに傷んでしまう野菜は重ねておかずに上から見てすべて見えるように収納。
そのためには「立てる」ことがポイント。
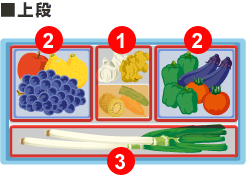
上段には中型野菜や果物、シメジなど柔らかく重ねると痛みやすいものをおきます。
-
使いかけ、薬味エリア
容器などに入れて指定席を設けます。
フタをする場合は半透明のものかラップをして中が見えるように。 -
使いかけ、薬味エリア
カゴが無い場合は、「使いかけエリア」の容器を仕切り代わりにすることもできます。
-
使いかけ、薬味エリア
長もの野菜はヨコに寝かすか、ある程度の長さに切ってビニール袋に入れ、立てて収納します(その場合は下段手前に)。
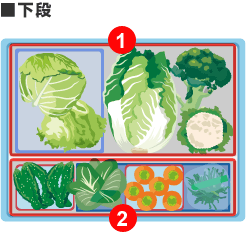
-
大きくて重い野菜は下段の奥
レタス、白菜、カリフラワーなどのごろりとした大きめ野菜は、安定するようカゴなどを利用して収納。
容器を仕切りにも利用
一つカゴなどの容器を使えば、仕切りの役割にもなり周囲に野菜を収納しやすくなります -
手前には葉ものや長ものを切って立てる
全体を見渡せるように立てて収納。
ペットボトルや100円ショップの書類立て、ブックスタンドは「立て収納」に大活躍。メッシュなど通気性のあるものを。
切った野菜には専用保存袋を活用すれば、より鮮度よく最後まで使い切りができます。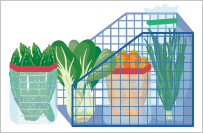
冷凍室
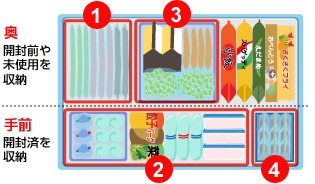
-
冷凍用保存袋のサイズは揃えて
同じ袋のサイズを使うことで大きさが揃って収納しやすくなります。量が多いものは複数の袋に分けてます。
少量なら袋を丸めて立てて収納します。 -
使いかけは目につくよう手前に
使いかけのものや使う頻度の高いものは、手前に配置。また、調理台に近い方向に置けばよりスピーディに出し入れ可能。
半分以上中身が残っているもの:
袋の形が保たれた量であれば、同じ形のもの同士でまとめます。残り少なくなったもの:
袋を丸め、立てて収納。少量のものでも目につき取り出しやすくなります。留めるゴムの色で種類分けするのも○。形を揃えて冷凍したものは立てて収納
残りものや食材はファスナー付きの密閉袋で平らに冷凍すればスッキリ立てて収納できます。垂直方向に並べれば、引き戸をすべて開けなくても見渡しやすくなります。 ブックスタンドで仕切ると便利。 -
容器は奥・手前ごとに真ん中に一つあればOK
種類ごとまとめて収納に便利なカゴなどは、最低限、手前に一つ、奥に一つ用意。左右に置く量に合わせて位置調節できる仕切りとしての役割にも。
-
アイスクリームバーはカゴに移す
アイスクリームバーの紙箱は取ってカゴに移しスペース節約。箱を開けて取り出す手間もなくなります。
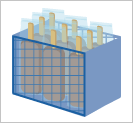
監修:収納アドバイザー 本多弘美
主婦の経験から生まれる家事ノウハウを体系づけ、1993年、横浜市女性協会主催「趣味から仕事へ」のセミナーをきっかけに、家事収納アドバイザーとしてスタート。講演会、新聞、テレビ、雑誌、展示場イベントや企業提案など活動の場を広げている。日本特有の職業に海外のメディアからも取材を受ける。