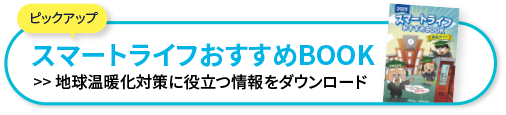地球温暖化を防ぐために、世界や国内、家電業界でさまざまな取り組みが行われています
地球温暖化を防ぐために、世界や国内、家電業界でさまざまな取り組みが行われています
世界的な地球温暖化対策の取り組み
気候変動枠組条約(1992年採択、1994年発効)
気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「気候変動枠組条約」という。)は、地球温暖化防止のための国際的な枠組みであり、究極的な目的として、温室効果ガスの大気中濃度を自然の生態系や人類に危険な悪影響を及ぼさない水準で安定化させることを掲げています。
現在、温室効果ガスの排出量は地球の吸収量の2倍以上です。将来の自然吸収量が現状とは異なる可能性もありますが、長期的な気候の安定化の視点から考えると、上記の目的の実現のためには、2050年までに温室効果ガスを半減させることは1つの中期的な道標と言えます。
気候変動枠組条約の概要
条約では、以下の原則のもと、先進締約国に対し温室効果ガス削減のための政策の実施等の義務が課せられています。

パリ協定(2015年採択、2016年発効)
2015年12月、パリで「主要排出国を含むすべての国が協調して温室効果ガスの削減に取り組む」という国際的な法的枠組みが採択されました。この「パリ協定」では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、1.5 ℃に抑える努力を追求することを目的としています。
気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)(2023年)
2023年11月30日(木)~同年12月13日(水)までアラブ首長国連邦・ドバイにおいて、国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)、京都議定書第18回締約国会合(CMP18)、パリ協定第5回締約国会合(CMA5)が行われました。
COP28では、パリ協定の目的に対する進捗を評価するグローバル・ストックテイク(GST)に関する決定、ロス&ダメージ(気候変動の悪影響に伴う損失と損害)に対応するための基金を含む新たな資金措置の制度の大枠に関する決定がそれぞれ採択されました。
気候変動枠組条約第29回締約国会議(COP29)(2024年)
2024 年11月11日~11月24日(2日間延長)、アゼルバイジャン・バクーにおいて、国連気候変動枠組条約第 29 回締約国会議(COP29)、京都議定書第 19 回締約国会合(CMP19)、パリ協定第6回締約国会合(CMA6)が行われました。
COP29では、気候資金に関する新規合同数値目標(NCQG)について、「2035年までに少なくとも年間3,000億ドル」の途上国支援目標を決定(多国間開発銀行による支援、途上国による支援を含む)。
また、全てのアクターに対し、全ての公的及び民間の資金源からの途上国向けの気候行動に対する資金を2035年までに年間1.3兆ドル以上に拡大するため、共に行動することを求める旨決定されました。
日本の地球温暖化対策の取り組み
地球温暖化対策計画(2025年)
2025(令和7)年2月18日、地球温暖化対策計画が閣議決定されました。
日本は、同日に世界全体での1.5℃目標と整合的で、2050年ネット・ゼロの実現に向けた直線的な経路にある野心的な目標として、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ60%、73%削減することを目指す、新たな「日本のNDC(国が決定する貢献)」を、気候変動に関する国際連合枠組条約事務局(UNFCCC)に提出しました。
今回、改定された内容には、この新たな削減目標及びその実現に向けた対策・施策を位置付けており、排出削減と経済成長の同時実現に資する地球温暖化対策を推進していきます。

「デコ活(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)(2022年~)」
我が国は2050年カーボンニュートラル宣言を行い、2021年4月には、2030年度に2013年度比で46%削減を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けていくことを表明しました。
環境省では、2050年カーボンニュートラル及び2030年度削減目標の実現に向けて、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しするため、新しい国民運動「デコ活」を展開。
「デコ活」では、脱炭素につながる将来の豊かな暮らしの全体像・絵姿をご紹介するとともに、国・自治体・企業・団体等で共に、国民・消費者の新しい暮らしを後押ししていきます。

エネルギー基本計画は、エネルギー政策の基本的な方向性を示すためにエネルギー政策基本法に基づき政府が策定するものです。
令和3年10月に第6次エネルギー基本計画を策定して以降、我が国を取り巻くエネルギー情勢は大きく変化しました。こうした状況の変化も踏まえつつ、政府が新たに策定した 2040年度温室効果ガス73%削減目標と整合的な形で、「エネルギー基本計画」が策定されています。
同時に閣議決定された「GX2040ビジョン」、「地球温暖化対策計画」と一体的に、エネルギー安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に取り組んでいきます。
電機・電子業界の取り組み
電機・電子関係団体は、「電機・電子温暖化対策連絡会」を構成し、政府が推進する地球温暖化防止「国民運動」に賛同し、業界統一行動指針を考慮の下、各企業の創意工夫を積極的に盛り込み、各種取り組みを推進しています。
電機・電子業界「カーボンニュートラル行動計画」~エネルギー起源CO2排出抑制~

電機・電子業界は、国際社会の一員として、さらに"地球規模での脱炭素化に貢献していく"ためには、グローバル・バリューチェーンの視点でGHG排出抑制・削減への取組みにチャレンジしていく必要があると考えています。したがって、2020年1月に気候変動対応に係る長期戦略として電機・電子業界「気候変動対応長期ビジョン」 を策定しています。
電機・電子業界のバリューチェーン全体におけるGHG排出量を、グローバル規模で2050年にカーボンニュートラルの実現をめざす。
具体的には、以下の取組みを実施していく。
-
Scope1+2(※)について、省エネ化および再エネ導入によって、排出量を最大限削減する
-
Scope3(※)について、バリューチェーンにおけるステークホルダーとの共創/協創と技術開発・イノベーションにより、可能な限り排出量の削減に努める
-
炭素除去を含めた様々な手法を用いて、残った排出量の相殺に努める
-
上記に加え、社会の各部門における脱炭素化に大きく貢献する
- Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)
Scope2:他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
Scope3:Scope1・2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出:15のカテゴリー)
カテゴリー1:購入部材、カテゴリー11:販売製品の使用 等
家電メーカーの取り組み
各家電メーカーごとに、各種取り組みを実施しています。
各企業のウェブサイト
世界規模で進む温暖化対策、わたしたち一人ひとりができることはあるでしょうか
地球温暖化の原因となっているCO2を削減するために、家庭で使うエネルギーの削減が求められています。
わたしたちが暮らしの中で地球温暖化の防止(CO2の排出低減)に協力できることは、一人ひとりがエネルギー使用の無駄を見直して、無理なく節電に取り組むことなのです。